電源ユニットはPCの性能を左右するようなパーツではありませんが、安定動作につながる意外と重要なパーツです。電源容量が不足すると動作が不安定になり、急にシャットダウンや再起動が起こることもあります。
特に高性能のCPUやGPUを搭載する場合は、消費電力も大きくなるため電源選びにも注意が必要です。CPUやGPUを交換する際に電源容量が足りなくなって、電源も買いなおす羽目になることもあります。
この記事では、筆者が考える電源を選ぶための最低限のポイント4つとこだわる人向けのポイント4つを解説していきます。
最低限のポイント4つ
電源容量
1つ目のポイントは電源容量です。電源容量が足りないと動作しなかったり、不安定になったりします。
基本的にはPC全体の消費電力の1.5倍を目安に選ぶと良いです。パーツのアップグレードの可能性が高い場合や、ハイエンドCPUを電力制限なしで運用する場合などは1.5倍以上の電源容量を選択するのも良いと思います。
ストレージの数などで変わってくるので以下の表などを参考に計算しましょう。
| パーツ | 消費電力の目安 |
|---|---|
| CPU | 13世代Coreシリーズの場合TDP60~150W Ryzen7000シリーズの場合TDP65~170W |
| GPU | GeForceRTX3000シリーズの場合130~450W前後 RadeonRX6000シリーズの場合107~335W前後 |
| メモリ | 1枚あたり5W |
| HDD | 3.5インチの場合1台あたり25W 2.5インチの場合1台あたり5W |
| SSD | SATA接続の場合1台あたり5W NVMe接続の場合1台あたり10W |
| ファン | 120mmの場合1基あたり3W前後 140mmの場合1基あたり5W前後 |
| マザーボード | 6~15W程度 |
全体の消費電力の1.5倍以上の電源容量を選ぶのは電源に余裕を持たせるためです。電源に余裕を持たせる理由としては、
- CPUフル稼働時の最大消費電力がTDPの1.5倍以上になることがある
- 高負荷で運用すると電源の劣化が早くなる
といったことがあります。
サイズ
2つ目のポイントは電源のサイズです。電源にも規格があり、現在はATX規格と小型のSFX規格の2種類が主流になっています。両者でネジ穴の位置が違うので対応するPCケースが変わります。
- ATX規格 幅150 × 高さ86 × 奥行き140 mm
- SFX規格 幅125 × 高さ63.5 × 奥行き100 mm
上記のサイズが一般的ですが、製品によって奥行きが異なる場合があるので注意しましょう。ケースによっては電源とグラボや簡易水冷のラジエーターなどが干渉することがあります。
ATX電源対応のPCケースが多く、スリムケースやMini-ITXケースなどの小型PCケースがSFX電源対応になっています。
EPSという規格もありますが、現在はほとんどがATXとEPS両方に対応しているのであまり気にする必要はありません。
対応する端子
3つ目のポイントは対応する端子です。製品によって対応する端子の種類や数が異なります。
自分の用途に合わせて以下の端子の数は確認しておきましょう。
- CPUコネクタ
→ CPUの補助電源に使用、4+4ピンのESP12V端子と4ピンのATX12V端子の2種類がある - PCIeコネクタ
→ グラボの補助電源に使用する6+2ピンの端子、CPUコネクタと共用の場合も - SATAコネクタ
→ SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブなどに使用する端子 - 12VHPWRコネクタ
→ ATX3.0規格の電源で採用されたグラボの補助電源に使用する12+4ピンまたは16ピンの端子
ハイエンドグラボではPCIe端子3~4個から12VHPWRコネクタに変換するケーブルが付属していますが、最近の電源では最初から1本のケーブルで対応しているものもあります。ケーブル1本のほうが扱いやすく、安定性も上がるのでおすすめです。
ケーブルの仕様
4つ目のポイントはケーブルの仕様です。製品によってケーブルの分岐や数、長さなどの違いがあるので事前に確認しておきましょう。ケースの大きさや配線の仕方によっては、ケーブルの長さが足りなくなる場合があるため注意が必要です。
ケーブルの取り回しにも種類があり、以下の3つがあります。
- 直出し方式
→ 電源の筐体内部から固定されたケーブルが伸びていて、ケーブルの着脱は不可 - セミプラグイン(セミモジュラー)方式
→ 一部のケーブルのみ着脱可能 - フルプラグイン(フルモジュラー)方式
→ 全てのケーブルが着脱可能
プラグイン方式のほうが使用するケーブルだけを取り付ければ良いため、配線がすっきりします。差し込み部分が出っ張るためケースの奥行きに多少注意が必要ですが、ケーブルの取り回しが簡単になるのでプラグイン方式がおすすめです。
こだわる人向けのポイント4つ
保証期間
5つ目のポイントは保証期間です。私はパーツが故障するかどうかは運次第だと思っています。有名なメーカー製でも壊れるときは壊れます。なので、なるべく長い保証の付いた製品を選ぶことをおすすめします。
最近の電源ユニットは保証期間が5~10年前後の長期保証のものが多いです。以下の記事ではメーカーの保証期間リストも載せているので、参考にしてみてください。
80PLUS認証のグレード
6つ目のポイントは80PLUS認証のグレードです。家庭用の電気をPC用に変換する際の変換効率によってグレードが変わります。最低でも80%以上になっています。
変換効率が良いものほど高価になりますが、その分発熱を抑えられるのでファンの回転数も下がり静音性が上がります。電源内部のコンデンサは熱に弱いため、製品寿命も延びます。
| 認証グレード | 電源負荷率 | ||
|---|---|---|---|
| 20% | 50% | 100% | |
| STANDARD | 80% | 80% | 80% |
| BRONZE | 82% | 85% | 82% |
| SILVER | 85% | 88% | 85% |
| GOLD | 87% | 90% | 87% |
| PLATINUM | 90% | 92% | 89% |
| TITANIUM | 92% | 94% | 90% |
グレードによる価格の差が結構大きいので、コスパを求めるならそこまで気にする必要はないです。小型ケースなどで排熱が気になる場合はこだわっても良いと思います。
まだ日本ではメジャーではないようですが、80PLUS認証よりも詳細に変換効率の規定を設けたETA認証や騒音値の規定を設けたLAMBDA認証というものもあります。
日本製コンデンサ使用の有無
7つ目のポイントは日本製コンデンサ使用の有無です。最近の製品では上限温度105℃のコンデンサが主流になっていて、中でも日本製のコンデンサは高品質で海外製のものに比べて壊れにくいと言われています。
一次側(入力)と二次側(出力)にそれぞれコンデンサが使用されていますが、製品によっては日本製コンデンサ使用という謳い文句で、一次側のみ日本製だったり、一部が日本製で後は海外製だったりという場合があります。どのメーカーでもPLATINUM以上のグレードであれば日本製コンデンサのみが多いですね。
海外製のコンデンサの品質について調べても10年以上前の話題が多く、現在の品質については正確にはわかりませんでした。Elite、Leron、Teapoなどの海外製コンデンサを使っている電源でも評価が高いものもあるので、今はそこまで神経質になる必要はないのかなと思います。
どうしても日本製にこだわりたい方は、このCybenetics Labsというサイトで調べることができます。ただし、記載がない製品もあります。このCybeneticsはETA認証やLAMBDA認証を提唱した会社になります。
OEM元(製造元)
8つ目のポイントはOEM元です。電源ユニットはOEM品を販売しているメーカーが多く、実際の製造メーカーと販売メーカーが異なることがほとんどです。
有名OEM元には
- Seasonic
- SUPER FLOWER
- FSP
- CWT
- Enhance
などがあります。
特にSeasonicやSUPER FLOWERは信頼性が高いと言われています。FSP・CWT・EnhanceもツクモやドスパラなどのBTOメーカーで採用されているので信頼できるメーカーですね。ただし、SeasonicはRTX3000シリーズとの相性問題が話題になり、少し信頼性が下がってしまいましたね。
実際には、どのOEM元でも製品自体のレビューなどを見て相性問題などの大きな不具合がなく、評価が高ければ問題はないでしょう。
OEM元にこだわりたい方はこちらもCybenetics Labsで調べることができますが、記載がない製品もあります。上記の5社以外の日本製コンデンサを使用するメーカーなども調べることができます。
まとめ
電源ユニット選びはこだわると結構難しいですが、電源容量、サイズ、端子、ケーブルをきちんと確認しておけば安定動作する電源を選ぶことができます。電源の変換効率についても、熱がこもるケースでない限り、電源容量に余裕を持っていればそこまで気にする必要はありません。
自分の予算や用途によって折り合いをつけて、適切な電源を選びましょう。

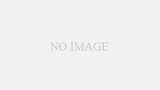
コメント